
ワーキングメモリーとは?短期記憶との違いや発達障害との関係、鍛える方法の有無を解説

監修
片岡 洋祐 先生 (神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 生体制御学講座 特命教授、日本疲労学会 副理事長)
ワーキングメモリーとは?いつ働くの?
私たちは日常生活において、会話中に相手の話を理解しながら自分の返答を考えたり、文章を読みながら少し前の内容を思い出したり、あるいは、店舗接客業の方であれば、お店で品出し作業をしている最中にお客様に質問されて対応した後、元の作業に戻ったりなどと、情報を短時間記憶しながらさまざまな作業を行っています。
このような、いわば「脳の作業台」のような働きを担っているのが「ワーキングメモリー」です。別の言い方で「作業記憶」とも呼ばれます。
ワーキングメモリーは、記憶・注意・言語化といった認知機能の各要素を経て、実行に移す際に最重要な脳の機能です。
ワーキングメモリーと記憶(短期記憶・長期記憶)との違いは?
ワーキングメモリーとよく似たものに「短期記憶」があります。短期という名の通り、記憶を保持する時間が1分以内程度の、保持時間が短い記憶をこう呼んでいます。
ワーキングメモリーと短期記憶の違いはどこにあるかというと、「記憶を保持しながら作業ができるかどうか」です。
短期記憶は文字通り、記憶を保持するだけの受動的なものです。一方、ワーキングメモリーは、記憶を保持しつつ、それを利用して作業も行う、能動的な一時的記憶です。
ワーキングメモリーは、記憶を保持している間に情報を更新したり調整したりすることもあり、これも短期記憶と違った側面といえます。
その他、短期記憶よりも保持時間が長く、情報を半永久的に保存できる記憶が長期記憶です。前日の夕飯の記憶も、子どもの頃に旅行した記憶も長期記憶に当てはまります。
長期間保存されるがゆえに、繰り返し記憶を呼び起こしたり、ある程度の時間が経過してから取り出されたりするうちに、一部の記憶があいまいになるなどして、記憶の内容が少しずつ変化する(書き換えられる)可能性があります。
ワーキングメモリーで処理された情報の一部が長期記憶として定着することもあります。
■「認知機能」の中におけるワーキングメモリーの位置づけ
ワーキングメモリーは単独で存在する記憶の一つというだけでなく、もっと広範な「認知機能」全体の中で重要な役割を果たしています。
認知機能とは、記憶、注意、言語理解、思考、判断、問題解決、学習といった、人が情報を処理し、行動する上で必要な機能全般のことです。
一時的に情報を記憶するとともに、それを利用して作業も行うワーキングメモリーは、さまざまな認知機能の「土台」や「エンジン」として機能していると考えられています。例えば、以下のような場面です。
思考・推論・問題解決の場面
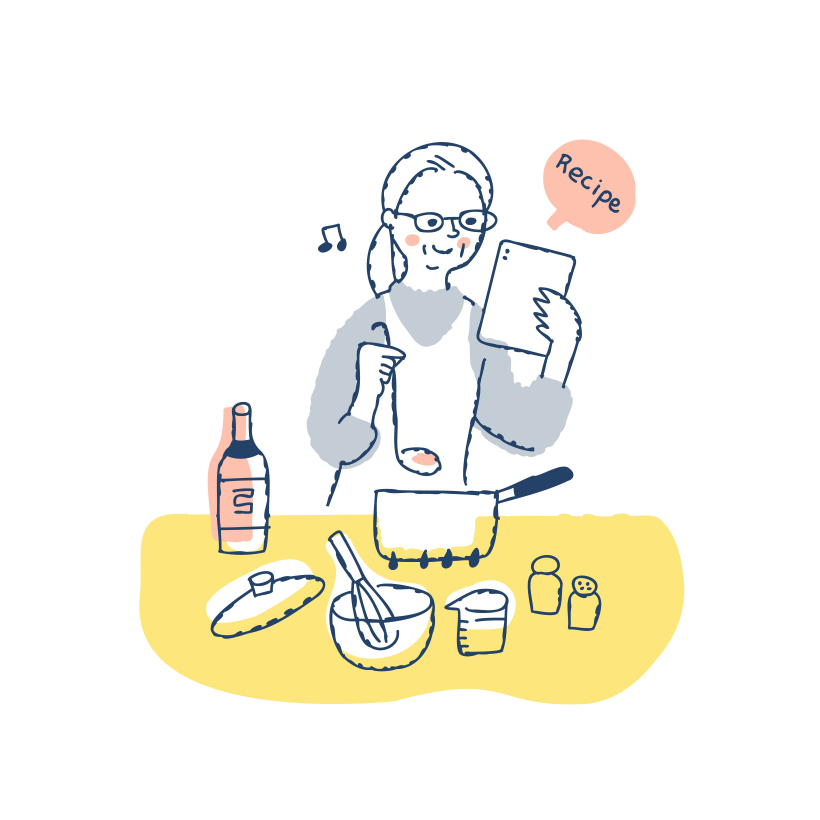
料理をするとき、私たちはレシピの手順を頭の片隅に記憶しながら、野菜を切ったり炒めたりという作業を行います。また、将棋やチェスのようなゲームでは、盤面の状況を記憶しつつ、「相手がこう動いたら、自分はこう対応する」といった未来の展開をいくつも考え、最善の一手を選びます。これらは、目標(料理を完成させる、ゲームに勝つ)に向かって、情報を一時的に記憶し、作業している典型的な例です。
言語理解の場面
相手と会話をしているとき、私たちは相手の話の内容を覚えておきながら、それに対する自分の返事を考えます。また、本を読む際には、文の初めの内容を記憶しているからこそ、文末まで読んだときに全体の意味が理解できます。このように、話したり読んだりする上でも、ワーキングメモリーは絶えず働いています 。
学習の場面
「教科書の50ページを開いて、最初の段落を読んでください」というような複数の指示を一度に聞き、その順番通りに実行できるのは、ワーキングメモリーが指示を一時的に記憶し、行動に移しているためです。また、新しい英単語を覚えるとき、その単語の音や綴りを一時的に記憶し、繰り返し練習することで、長期的な記憶として定着させていきます。この記憶の定着にも、ワーキングメモリーが重要な役割を果たしています。
ワーキングメモリーの働きが弱いと…

ワーキングメモリーの働きが弱い場合、日常生活で以下のような困難が生じることがあります。
- - 指示を聞き逃しやすい、または複数の指示を一度に覚えられない
- - 会話中に話が逸れたり、何を話していたかを忘れたりする
- - 文章を読むのに時間がかかる、読んでも内容が頭に入りにくい
- - 計画を立てたり、段取り良く物事を進めたりするのが苦手
- - 計算ミスが多い(特に暗算)
- - 忘れ物や失くし物が多い
- - 注意散漫になりやすい
このような困難が生じた結果、不安や悩みを感じる人も少なくないでしょう。
ワーキングメモリーは発達障害と関連がある?
ワーキングメモリーは、さまざまな発達障害(神経発達症)の認知特性と関連が見られることもあります。
関連の仕方は、障害の種類や個人によって異なりますが、一部をご紹介すると、例えば、ADHD(注意欠如・多動症)の子どもは、ワーキングメモリーに負荷のかかる場面で注意を持続させることが難しい傾向があり、教師の指示を忘れやすいという行動特性を示すことがあります。
また、読み書きや計算など特定の学習領域に困難を示す限局性学習症(SLD)の方の中には、ワーキングメモリーに課題を抱えるケースが見られます。特に、全般的な知的発達に遅れがないにもかかわらず、言語発達に特異的な困難を示す特異性言語障害(SLI)の子どもは、多くの場合、言語情報を一時的に保持し処理する言語性のワーキングメモリーや、言葉の音を記憶する音韻的短期記憶に弱さを示すことが報告されています。
このように、ワーキングメモリーの特性は神経発達症の方の困難さの一側面として理解されることがあります。しかし、その関連性は複雑であり、ワーキングメモリーの特性だけで神経発達症が判断されるものではありません。
また、発達障害とは別に、加齢によってもワーキングメモリーの機能は低下します。ワーキングメモリーの機能は20代から30代頃にピークを迎えた後、非常に緩やかに低下していくとされています。この変化はすぐには自覚されませんが、40代、50代になると『マルチタスクのときにミスが増えた』といった形で、機能の低下を実感する人が増えるかもしれません。そして、認知症(例えばアルツハイマー病など)の初期症状として、ワーキングメモリーを含む記憶力の低下が見られることもあります。
軽度認知障害(MCI)の段階でも、ワーキングメモリーの活動に関連する脳領域の変化が報告されています。ただし、こうした変化の現れ方には大きな個人差があることも知られています。
ワーキングメモリーはIQと関連がある?
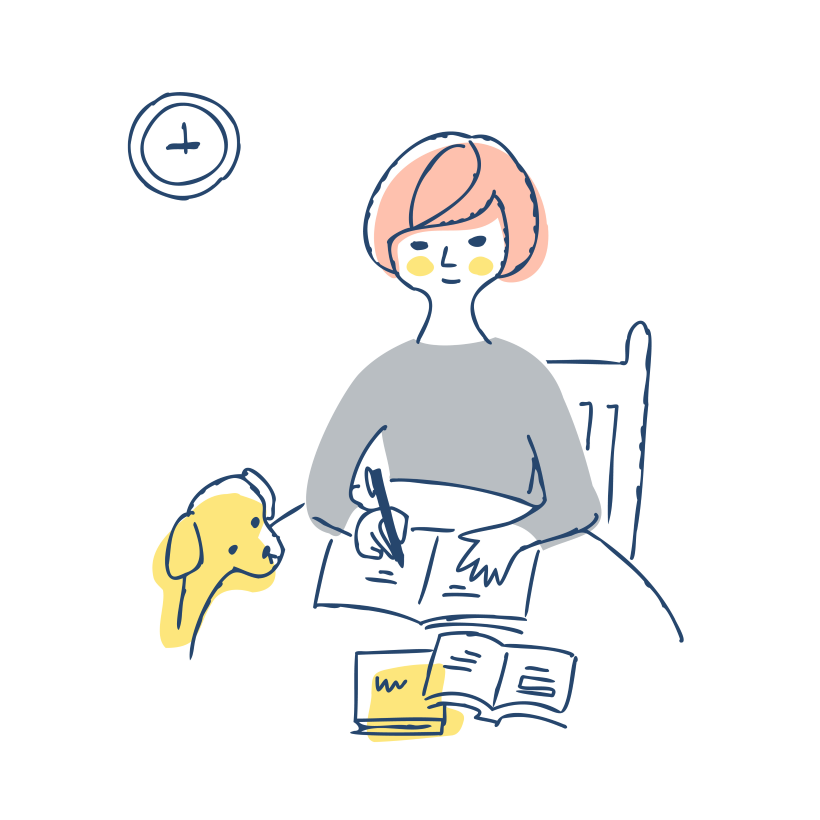
IQ(Intelligence Quotient:知能指数)は、知能を測定するために設計された、いくつかの検査の結果を表す数値のことです。ワーキングメモリーとIQとの間には、正の相関関係があることが多くの研究で示されていて、ワーキングメモリーの容量が大きいほど、複雑な情報を効率的に処理し、推論や問題解決を行う能力が高い傾向があります。
ただし、IQは多面的な能力を示す数値の一つであり、ワーキングメモリーの機能だけでIQのすべてが決まるわけではありません。
ワーキングメモリーを鍛える方法はある?
ワーキングメモリーを鍛えることで学習や仕事の能力を高め、日々の生活の質を向上できるのではないかと期待する声もあるでしょう。
これについては多くの研究が進められています。研究によると、特定の課題(例えば、ある記憶ゲーム)を繰り返し練習すれば、その課題の成績は向上することがわかっています。しかし、それが日常生活におけるワーキングメモリー機能の全般的な向上や他の認知能力にも及ぶのかについては、専門家の間でも意見が分かれています。
したがって現時点では、「これをすれば確実にワーキングメモリーが鍛えられる」という確立された方法はまだないと考えるのが妥当といえます。
ただ、例えばいわゆる「脳トレ」のような四則演算のトレーニングなどは、繰り返しているうちに成績が良くなることがあります。
ワーキングメモリーの機能そのものが練習によって向上するのかどうかは現時点では断定できませんが、そうしたトレーニングが、加齢による注意力の低下などを抑えるのに一役買っている可能性はあるかもしれません。
ワーキングメモリーの機能を維持する(低下させない)ための方法
ワーキングメモリーを直接鍛えることは、現状では難しいものの、その機能を良好に保つ、あるいは低下を防ぐために日常生活で心がけられることの例をご紹介します。
ワーキングメモリーに関連する栄養素を摂取する
脳機能全般の健康維持にはバランスの取れた食事を取ることが基本です。その上で、ワーキングメモリーの働きに関連するといわれる栄養素を意識的に摂取するのも良いでしょう。
ピロロキノリンキノン(PQQ)は、私たちの身近な食品にも含まれている栄養素で、例えば納豆や緑茶、母乳などに微量ながら存在することが知られています。PQQは、細胞内のエネルギー産生工場であるミトコンドリアの機能をサポートする補酵素の一種です。ミトコンドリアにおけるATP(アデノシン三リン酸)産生、すなわちエネルギー産生を促す働きが注目されています。
また、PQQは強力な抗酸化作用を持ち、活性酸素によるダメージから細胞を保護する役割も期待されています。特に、脳の神経細胞は活性酸素によるダメージを受けやすいため、この抗酸化作用による神経細胞の保護効果は、脳の健康を維持する上で重要だと考えられています。
実際に、40歳以上80歳未満の健康な日本人を対象とした研究では、PQQを1日あたり21.5mg、12週間摂取することで、ワーキングメモリーも関連する高次脳機能の一部である、認知機能の柔軟性(状況に応じて注意や思考を切り替える能力)や処理速度が改善したことが報告1)されています。また、高齢者を対象とした他の研究でも、PQQの摂取によって言語記憶などが改善したという報告2)があります。
これらの研究は、PQQがワーキングメモリーを含む認知機能の維持をサポートする可能性を示唆しています。ただし、どのような人や認知機能の側面に最も効果的なのかについては、さらなる研究が必要な場合があります。
1)J Am Nutr Assoc. 2022 Nov-Dec;41(8):796-809.
2) Adv Exp Med Biol. 2016:876:319-325.
■集中力の維持・改善に関連する栄養素
ワーキングメモリーは注意機能と密接に関連しているため、集中力をサポートする栄養素も重要といえます。
例えば、ブドウ糖(糖質)は、脳の主要なエネルギー源であり、適切な供給は集中力や思考力の維持に不可欠な栄養素です。ただし、血糖値の急激な変動は集中力を乱す可能性もあるため、GI値※の低い糖質(そば、全粒粉パン、玄米、リンゴ、イチゴなど)を選ぶといった工夫をするのもおすすめです。
ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変換する際に必須の栄養素であり、神経機能を正常に保つ働きも持っています。不足すると、疲労感や集中力の低下を招くことがあります。ブドウ糖とあわせて摂ると良いでしょう。
その他、DHA・EPA、レシチン、トリプトファンなどの栄養素も、脳機能との関連が研究されています。それぞれ、青魚、大豆、乳製品などに含まれています。
※GI値:Glycemic Index(グリセミックインデックス)の略で、食後の血糖値の上昇度を示す指数
集中力が低下しないような環境づくりを心がける

ワーキングメモリーの働きを最大限に活かすためには、集中できる環境であることも重要といわれています。環境が学習意欲に影響し、それが集中力や学習効率にも関わってくるため、物理的な環境への配慮も大切です。
集中できる環境づくりには、快適な室温を保つ、適切に換気がされていることなどがポイントとなります。
暑すぎたり寒すぎたりする環境は、学習意欲を低下させる可能性があります。特に、室温が高め(やや暖かいと感じる程度)の環境では、学習意欲が低下する傾向が報告されています。自分にとって快適で、作業に集中しやすい室温に調整するよう心がけましょう。25℃の室温が最も集中しやすいという研究結果もあります。
換気量が少なく、二酸化炭素濃度が高いような空気環境は、学習意欲に影響を与える可能性があります。適切な換気を行い、新鮮な空気を取り入れることで、学習意欲の維持につながることが期待できます。換気量を増やすことで講義中の学習意欲が向上したという研究結果もあります。
また、騒音が少ないこと、視覚的に気が散るものがないことなども重要です。
静かな場所を選ぶ他、ノイズキャンセリングイヤホンを使用して雑音を減らす、作業スペースを整理して視覚的に気が散るものを減らすなど、快適な作業環境を整えましょう。
脳を休憩させる時間をつくる
連続して脳を使い続けると、ワーキングメモリーの効率が低下するため、適度な休息も重要です。
なかでも睡眠は、記憶の整理や脳の疲労回復に不可欠です。大人の場合、一日6~8時間が推奨されているため、8時間睡眠を目標に、最低でも6時間以上しっかりと眠りましょう。
運動も脳の血流を促進し、神経の可塑性(かそせい/適応する能力)を高める可能性があり、認知機能にも良い影響を与えることが知られています。休息中に、適度に行うと気分転換にもなるでしょう。
また、ストレスを軽減し、脳をリフレッシュさせるのもおすすめです。趣味やリラックスできる時間を持つ他、瞑想などを行うのも良いでしょう。
ワーキングメモリーの容量不足で起こる困りごとにはこう対処しよう!
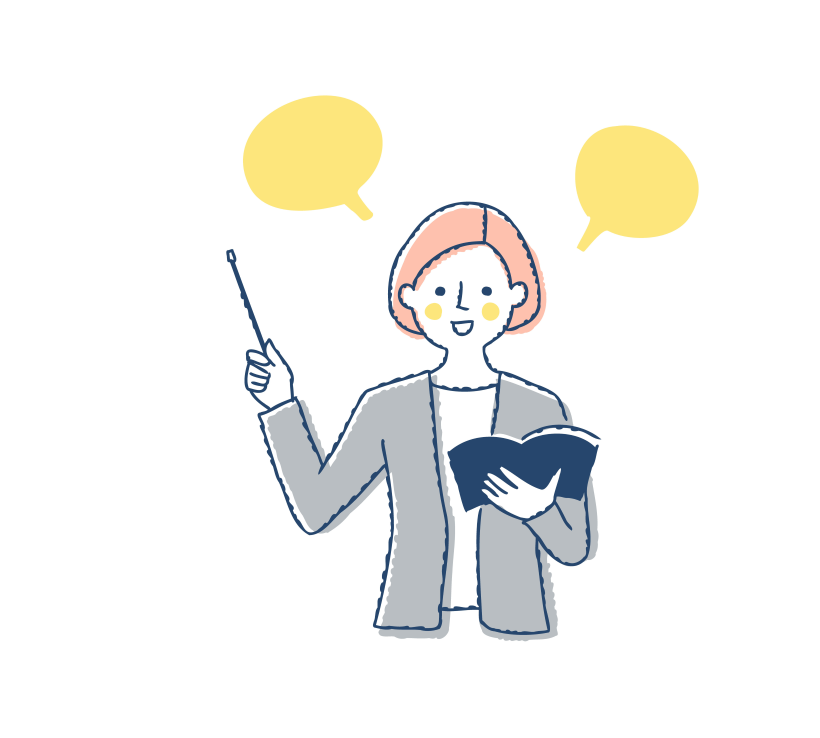
ワーキングメモリーの容量や働きには個人差があり、「覚えが悪い」「すぐに忘れてしまう」「集中が続かない」といった困りごとを感じる場合でも、以下のような対処をすることで、その影響を和らげることが可能です。
・外部リソースを積極的に活用する(外部記憶の利用)
- - ワーキングメモリーの負担を減らすために、覚えておくべきことやタスクは積極的に、メモやTo-Doリストなどに記録しましょう。
- - スマートフォンのリマインダーやタスク管理アプリ、アラームを活用し、予定やタスクの実行時間を通知するように設定するのも効果的です。
・情報を整理し、負担を軽減する工夫を取り入れる
- - 一度に多くの情報を処理しようとすると、ワーキングメモリーに大きな負荷がかかります。情報を扱いやすくする工夫を取り入れましょう。
- - 一度に処理する情報量を少なくし、複雑な情報は小さなステップに分解するなど、情報量を調整すると良いでしょう。
- - 電話番号や文章などを意味のあるかたまりに区切って覚えるのもおすすめです。
- - 手順や情報を図やイラスト、フローチャートなどで視覚的に示すと理解しやすくなります。チェックリストの作成も有効です。
・記憶への定着を促す工夫
- - 情報をワーキングメモリーとして留め、さらに長期記憶に移行しやすくするための工夫です。
- - 例えば、覚えたい情報や指示内容を声に出して繰り返すことで、記憶に残りやすくなります。
- - また、覚えるべき情報を目で見るだけでなく、聞く、書く、話すなど、複数の感覚を使ってインプットすると、記憶に残りやすくなります。
状況に応じて、自分の特性や困りごとについて家族、学校の先生、職場の上司や同僚などに伝え、必要な配慮や協力を求めることも有効な手段です。指示を受ける際は、短く具体的な言葉で伝えてもらうようお願いするのも良いでしょう。
これらの対処法は一例です。大切なのは、さまざまな方法を試しながら、焦らずに自分に合ったやり方を見つけていくことです。
自分自身を理解し、工夫を重ねることで、ワーキングメモリーを維持していくことができるでしょう。
【プチメモ】ワーキングメモリーの仕組み(モデル)と測定方法
ワーキングメモリーが私たちの頭の中でどのように働いていて、また機能をどのように測定できるのかを簡単にご紹介しましょう。
まず、ワーキングメモリーがどうやって働いているのかという仕組みについてです。
それを説明する有名な考え方の一つに、「多成分モデル」というものがあります。ワーキングメモリーがいくつかの専門チームに分かれて仕事をしている、というイメージです。あるチームは指揮者のように、どの情報に注意を向けるか、どのチームに頑張ってもらうかを指示し、作業全体をスムーズに進めます。別のチームは、音や映像などで見聞きしたものを一時的に記憶します。そうして記憶した情報と、私たちが元々持っている記憶(長期記憶)などを集めて、「一つのまとまったストーリー」として編集し、理解しやすくするチームもいます。このように、いくつかのチームが協力し合うことで、私たちは会話をしたり、計算をしたり、本を読んだりといった、日々のさまざまな活動ができているのです。
こうしたワーキングメモリーの働き具合(「作業台」の広さや使い勝手)を調べるためには、いくつかの方法(検査課題)が使われます。
なかでも有名なのが、「Nバック課題」です。次々に出てくる絵や文字を見て、「今見たものは、N個前に見たものと同じかどうか」を判断する、ゲームのような課題です。以前の情報を覚えておきながら、新しい情報と比べる必要があり、ワーキングメモリーの機能を調べるのに有効な方法といえます。
また、「ストループテスト」という検査課題もあります。「『あか』という文字が青インクで書かれているのを見て、文字の意味ではなくインクの色(ここでは青)を答える」といった課題に取り組むことで、文字を読んでしまう自動的な反応を抑え、求められた情報に正しく注意を向ける力、すなわちワーキングメモリーの司令塔の働きが試されます。
その他、「数字の順唱・逆唱」といって、読み上げられたいくつかの数字を覚えて、同じ順番(順唱)、または逆の順番(逆唱)で答える課題も、ワーキングメモリーの機能を測る検査課題です。
これらの課題は、ワーキングメモリーの働きをより詳しく知るための研究や、場合によっては医療機関などで認知機能の状態を把握するために使われることがあります。
参考文献
- 船山 道隆, 神経心理学, 2022, 38(3)
- 湯澤 美紀, 心理学評論, 2011, 54(1)
- 湯澤 正通, 発達心理学研究, 2019, 30(4)
- Shiojima Y, Akanuma M, et. Al, J Am Nutr Assoc. 2022, 41(8)
- Itoh Y, Sakatani K, et. Al, Adv Exp Med Biol. 2016, 876
- Anna-Mariya Kirova, Rebecca B. Bays, Sarita Lagalwar; BioMed Research Intl. 2015






