
せき(咳)が長引く原因は風邪ではない?止まらないせきへの対処法を紹介

監修
新実 彰男 先生 (大阪府済生会茨木病院 呼吸器内科部長 兼 老健施設長)
せき(咳)が3週間以上続く場合は、風邪が長引いているわけではないかも
せきが出ると、「風邪を引いたかも」と思うことが多いかもしれません。しかし、当然ですが、せきの原因は風邪だけではありません。せきの症状が長引いているほど、風邪のような急性感染症が原因の可能性は少なくなり、慢性の感染症、あるいは感染症以外の病気が原因である割合が高くなってきます。
せきが、例えば3週間以上も続いていたりする場合は、風邪などに多い「急性のせき」とはいえないため、しっかり診察を受けたほうが良いでしょう。
まずは、この後の「せき(咳)が長引いているときに考えられる風邪以外の病気・症状」「せき(咳)が長引いている場合の受診の目安をセルフチェック」の内容も参考に、ご自身の状態を確認してみてください。
せき(咳)の長さによる分類
せきの原因はさまざまなものが考えられ、「どのくらい長くせきが続いているか」で原因が異なる傾向があります。医学的には、せきの持続期間によって、以下の3つに分類されます。
| せきの分類 | 急性咳嗽 | 遷延性咳嗽 | 慢性咳嗽 |
|---|---|---|---|
| 持続期間 | 3週間未満 | 3~8週間未満 | 8週間以上 |
| 原因 | 感染症によるものがほとんど | 感染症によるものとそうでないものどちらも考えられる | 感染症以外によるものがほとんど |
①急性咳嗽(きゅうせいがいそう)
症状の持続期間が、3週間未満の急性のせきを「急性咳嗽」といいます。咳嗽(がいそう)とは、せきを表す医学用語です。
急性のせきは、感染症によるものが多くを占めます。また、感染症の中でも、細菌ではなく、ウイルスによる呼吸器感染症が多くを占める傾向があります。そしてその呼吸器感染症の大半は、風邪によるものです。
一方、細菌による呼吸器感染症としては、マイコプラズマ、百日咳、クラミジアなどがあります。
医療機関で治療を行う場合、ウイルス性の場合は、インフルエンザを除いて対症療法(症状に合わせた治療)が行われ、細菌性の場合には抗菌薬による原因療法(病気の原因を取り除く治療)が行われます。
②遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう)
症状の持続期間が3~8週間未満の、やや長引いているせきを「遷延性咳嗽」といいます。遷延(せんえん)とは、何かが長引いているという意味です。
遷延性咳嗽には、風邪などの急性感染症がほぼ治った後にせきだけが長引いているケースと、感染症以外の原因によるケースがあります。
③慢性咳嗽(まんせいがいそう)
症状の持続期間が、8週間以上の長引いているせきを「慢性咳嗽」といいます。
慢性咳嗽では、感染症ではないせきが多くを占めます。例えば、アレルギー性の呼吸器の病気(例:喘息・咳喘息、アトピー咳嗽、副鼻腔炎)、感染症やアレルギー以外の呼吸器の病気(例:COPD、肺がん)、呼吸器以外の病気(例:胃食道逆流症)などです。また、薬の副作用(例:一部の高血圧用薬)なども原因として考えられます。ただし、これらの原因によるせきの患者さんが、発症早期に急性咳嗽として受診する場合もあるので、注意を要します。
せき(咳)が長引いているときに考えられる風邪以外の病気・症状

せきは大変ありふれた症状ですし、せきにともなうことの多い鼻やのどの症状も、ごく一般的な症状です。そのため、症状だけでは、病気の原因を見分けにくいことが少なくありません。
せきが長引いている場合の対処は、一度は医師の診察を受けることが基本です。ここでは、症状による大まかな傾向を解説しますので、ご自身の症状と照らし合わせながら、医療機関を受診するようにしましょう。
風邪の後にせきが残っている場合
感染後咳嗽(かんせんごがいそう)などの可能性が考えられます。感染後咳嗽とは、感染症の原因となった病原体が、既に体から排除され、せき以外の症状は軽快しているにもかかわらず、せきだけが残っている状態のことです。
気道(のどから肺に続く空気の通り道)の粘膜が過敏になっていて、せきが起きやすくなっていることなども一因と考えられています。通常は時間とともに自然に治まっていきます。
夜から明け方に症状がひどくなる場合
喘息(ぜんそく)や咳喘息などが考えられます。
喘息は気道に慢性的な炎症が起き、気道の内腔(空気が通るスペース)が狭くなり、呼吸が苦しくなる発作が起きる病気です。この発作にせきをともなったり、ゼーゼー、ヒューヒューといった呼吸音(喘鳴【ぜいめい】)がしたりすることが少なくありません。
一方の咳喘息は、せきのみが症状の病気です。ただし、咳喘息から喘息に移行することもあります。
鼻水をともなう場合
鼻水をともなうせきの場合、鼻炎や副鼻腔炎による後鼻漏などが考えられます。
鼻汁(鼻水)は、通常であれば気づかないうちに食道へ流れていくのですが、鼻炎や副鼻腔炎のために鼻水の分泌量が多いときには、その一部がのどの気道に流れて粘膜を刺激する「後鼻漏(こうびろう)」という現象が起こります。この後鼻漏が、せきを誘発するというメカニズムです。
のどの不快感をともなったりアレルギー体質の場合
アトピー咳嗽などの可能性が考えられます。
アトピー咳嗽とは、アレルギーが関与して起こるせきのことで、のどがかゆいように感じたり、イガイガしたりすることが多いです。
喫煙歴が長い場合

喫煙によりリスクが高まる呼吸器疾患などが考えられます。
例えば、肺がんやCOPD(慢性気管支炎や肺気腫)などです。
横になっているときや体を動かしたときに症状が強まる場合
心不全などの可能性があります。心臓のポンプ機能が低下しているために、肺がうっ血(血液中の水分が溜まること)しやすくなり、それが気道を刺激することなどによって、せきが誘発されるというメカニズムです。
心不全による肺のうっ血は、寝ているよりも上半身を起こしていたほうが抑制されるため、呼吸症状が楽になることが多いです。喘息症状も同様に、横になると悪化することがあります。
胸やけや胃もたれなどをともなう場合
胃食道逆流症が考えられます。これは、食べた物や胃液が食道のほうに逆流してくる病気です。逆流したものの一部が、食道や気道の粘膜を刺激して、せきを引き起こすと考えられています。
長引くせきの主な原因と症状のまとめ
上記で紹介した病気だけでなく、せきが関連する病気の原因や症状をまとめました。典型的な症状の場合を記載しており、必ずしもこの通りとは限りませんが、受診前の参考にしてみてください。
長引くせきの主な原因と症状
| 疾患名 | せきの特徴 | せきの持続期間 | せき以外の症状 |
|---|---|---|---|
| 感染後咳嗽 | たんをともなわないせき | 3~8週未満の遷延性咳嗽として多くみられるが、それ以上続くこともある | 特にない |
| 百日咳 | 連続するせきが発作的に起こる。発作の最後に嘔吐をしたり、子どもでは笛のような呼吸音がすることがある | 数週間から3ヵ月ほど | 病気の初期に風邪のような症状が現れることが多い |
| 結核 | 長引くせき。血液が混ざったたんが出ることもある | 結核の治癒まで | 倦怠感、微熱、寝汗、体重減少など |
| 喘息 | 息苦しさや喘鳴をともなうせきの発作を生じる。夜から早朝に発作が現れやすい | 病気のコントロールが不十分な期間は持続 | 発作時には呼吸困難となり、緊急治療が必要になることも |
| 咳喘息 | 夜から早朝に、たんをともなわないせきの発作が現れやすい | 病気のコントロールが不十分な期間は持続 | 特にない |
| 鼻炎・副鼻腔炎 | たんのような分泌物をともなうせき | 鼻炎・副鼻腔炎が続いている期間 | 鼻水、鼻づまり |
| アトピー咳嗽 | のどの不快感をともなう、たんをともなわないせき | 病気のコントロールが不十分な期間は持続 | 花粉症をともなうことが多い |
| COPD | たんをともなうせきが出て、体を動かしたときに呼吸困難を生じやすい | 病気の比較的初期からみられることが多い | 息切れや呼吸困難 |
| 肺がん | 長引くせき。胸痛をともなったり、血液が混ざったたんが出ることもある | 病気の経過とともに、変化しながら続くことが多い | 声のかすれ、のどの違和感、体重減少など |
| 胃食道逆流症 | 食後や起床直後、横になったときに現れやすいせき | 病気のコントロールが不十分な期間は持続 | 胸やけ、呑酸(のどに酸っぱいものが上がってくる)など |
| 心不全 | 過度な運動や横になっているときにせきが起こりやすい | 病気の経過とともに、変化しながら続くことが多い | 息切れ、動悸、倦怠感、むくみなど |
せき(咳)が長引いている場合の受診の目安をセルフチェック

せきの大半は、ウイルスによる呼吸器感染症です。ウイルス性の感染症によるせきであれば、インフルエンザの急性期を除いて原因に効く薬(ウイルスを除外する薬)はなく、症状に合わせた治療を続けることになります。ただし、せきが長引いている場合はウイルス感染症の可能性が低いため注意が必要です。
また、せき1回で2kcalを消費するといわれるくらい、体力を消耗するため、病気に対する抵抗力を低下させてしまいかねません。仮に1日に100回せきが出ているとしたら、それだけでご飯1膳分前後のカロリーを失ってしまうことになります。
以下のようなせきが出る場合は早めに病院を受診するようにしましょう
色のついたたんをともなう場合
黄色や緑のたんをともなうせきは、細菌の感染症が起きている可能性があります。また、せきに赤いたんをともなうときは、気道の粘膜などから出血している可能性もあるため、注意が必要です。
高齢の方や子ども、基礎疾患がある場合
新型コロナのパンデミックの際、再三報道されていたように、高齢の方や基礎疾患のある方は、感染症にかかると重症化しやすいことが知られています。また、子どもも感染症などが重くなりやすい傾向があるため、せきが長引くときには早めに受診をしてください。
せき以外の症状がある場合
せきとともに以下のような症状がある場合は、記載の診療科を参考に医療機関を受診してみてください。
特に、呼吸困難があるときには、急いで病院を受診するようにしましょう。
| 症状 | 診療科 |
|---|---|
| 息切れ、呼吸困難 |
かかりつけ医、または呼吸器科を受診 ※症状が強かったり急速に悪化する場合は救急外来を受診、または救急車を要請※ |
| 鼻水、鼻づまり、のどの違和感 | かかりつけ医、または耳鼻咽喉科を受診 |
| アレルギー症状 | かかりつけ医、またはアレルギー科を受診 |
| 胸やけ、呑酸(酸っぱいものが上がってくる感じ)、胃もたれ | かかりつけ医、または消化器科を受診 |
| 慢性的な動悸や息切れ、倦怠感、むくみ | かかりつけ医、または循環器科を受診 |
緊急時の判断
緊急時の判断には、総務省消防庁が発信する「緊急度判定プロトコル」というものがあります。こちらのサイトにある、家庭自己判断用の救急受診ガイドが役立ちます。
なお、何科に行けば良いか判断に迷う場合には、以下を参考に相談してみると良いでしょう。
| 対応 |
|---|
| 救急安心センター事業「#7119」※1に相談する |
| こども医療でんわ相談事業「#8000」※2に相談する(子どもの場合) |
| かかりつけ医に相談する |
※1:「救急車を呼んだ方が良いか」「今すぐ病院に行った方が良いか」など、判断に迷ったときに「#7119(又は地域ごとに定められた電話番号)」に電話することで、救急電話相談を行える
※2:保護者の方が、夜間の子どもの症状にどのように対処したら良いのか判断に迷った場合などに「#8000」に電話し、小児科医師や看護師に救急電話相談を行える。「#8000」は地域によって繋がる時間が異なるため注意。詳細は厚生労働省サイトをご確認ください。
せき(咳)が長引くときの対処法
のどの刺激を抑える
マスクを使う

マスクを着用すると、吸い込む空気が加湿されて、のどへの刺激が抑えられます。また、花粉やハウスダストなどの異物が体内に入り込む量が減り、アレルギーにともなうせきなどの症状も抑えられます。なお、呼吸器の感染症については、自分の感染予防だけでなく人にうつさないためにもマスク着用を忘れずに。
室内の気温・湿度を調整
気温(室温)や湿度の変化がせきを誘発することもあります。また、冬季の乾燥や冷気は、のどにダメージを及ぼしやすいものです。
エアコンや加湿器を使ってのどへの刺激を抑えましょう。せきに花粉やハウスダストなどへのアレルギーが関係している場合には、丹念な清掃や空気清浄機の使用も考えてみましょう。
刺激の強い食べ物・飲み物を控える
カフェインやアルコール、香辛料、酸味の強いもの、熱すぎる・冷たすぎるものなども、のどに刺激を与えるので控えめにしましょう。
なお、せきの症状に食品アレルギーが関与している場合は、その食品の摂取を避ける必要があります。
タバコを吸わない
タバコはのどや気管支、肺などにダメージを与える大きな原因です。ある研究では、非喫煙者の慢性咳嗽の有病率は3%なのに対して、喫煙者では8%と報告1)されています。
1)Yunus ÇolaK et al. Risk Factors for Chronic Cough Among 14,669 Individuals From the General Population. Chest. 2017 Sep;152(3):563-573.
こまめに水分を補給する
のどの乾燥を防ぐために水分をこまめに摂取しましょう。特に、たんをともなう湿性咳嗽(しっせいがいそう)では、水分を多く摂るとたんが柔らかくなって、排出されやすくなるといわれています。
なお、せきの他に熱があるときや食事を十分食べられないようなときには、脱水予防のため、水分摂取がより大切です。
症状緩和のために市販薬を使用する
既にお話ししたように、長引くせきでは、一度は医師の診察を受けることが基本です。ただ、そうはいっても、時間をなかなかとれないということもありますよね。そのような場合、薬剤師や登録販売者のいる薬局・薬店で相談し、市販薬を試してみるのも方法です。
市販薬には、せき症状に対して主に、以下のような成分が使われています。
・ジヒドロコデインリン酸塩:せき中枢(せきを制御する脳の領域)に作用し、せきを和らげる
・デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物:せき中枢(せきを制御する脳の領域)に作用し、せきを和らげる
・dl-メチルエフェドリン塩酸塩:せき・たんを和らげる
・アンブロキソール塩酸塩:たんを和らげる
・ブロムヘキシン塩酸塩:たんを和らげる
・グアイフェネシン:たんを和らげる
市販薬を2~3日服用しても症状が改善されない場合には服用を中止してできるだけ早く医療機関を受診するようにしましょう。
- せきをしずめ、たんを和らげるアリナミン製薬の製品
-
- かぜの諸症状(せき、たん、くしゃみ、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)を緩和するアリナミン製薬の製品
-
※ベンザブロックLにはたんの効能はありません。
せき(咳)を長引かせないために日頃から意識したい生活習慣
せきの原因はさまざまですが、実際には呼吸器の感染症であることが多いもの。
感染症を防ぐには、いわゆる「三密」を避けるとともに、ウイルスや細菌をはねつけて体内で増殖させない力、つまり「免疫」が大切です。
ここでは、体内の免疫機能を維持するために意識したい生活習慣を紹介します。
規則正しい生活習慣を心がける
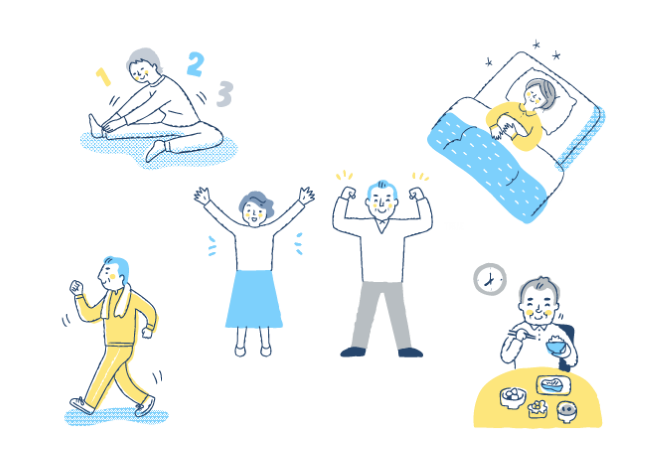
免疫機能を低下させないために、規則正しい生活を送るようにしましょう。具体的には、バランスの良い食事、適度な運動、質の良い睡眠を心がけてください。
また、肺炎、とくに高齢の方に多い誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)の予防には、口の中を清潔にしておくことが役立つと分かってきています。そのため、毎日の歯磨きと、適切な歯科治療を受けることも、大切なポイントといえます。
<関連記事>
免疫力を高めるには?生活習慣や食べ物など免疫力を高める方法を紹介
その他、せきに良いとされるツボを押してみるのも良いかもしれません。
せき止めに効果のあるツボは以下の記事をご覧ください。
疲れやストレスを溜め込まない
体の疲れや精神的ストレスも、免疫機能を低下させることが知られています。十分な休養と、ストレス解消を心がけましょう。
翌朝になっても疲れが取れないような日々が続くのであれば、抗疲労成分が配合された栄養ドリンクなどを飲んでみるのも良いでしょう。
- 抗疲労成分フルスルチアミン配合し、疲れの対処におすすめのアリナミン製薬の製品
-
のどに負担をかけない
「せき(咳)が長引くときの対処法」の箇所で、「のどの刺激を抑える」ための方法を取り上げました。それらの方法は、せきが出ていないときのせき予防にも役立ちます。ぜひ、ふだんから活用して、あまりのどに負担をかけないようにしてみてください。
せきが長引くときには、せき自体とせきが出る原因どちらにも対処しよう

せきには、気道の異物を排出するという大切な役割があります。そのため、せきさえ止めれば良いというものではなく、せきの原因を取り除く治療が必要です。
とはいえ、せきが続いていると体力が奪われてしまい、他の病気にかかりやすくなることも。さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、公共の場でせきをするのがたいへんはばかられるようになりました。このようなことから、せきそのものに対する治療も欠かせません。適切に市販薬を使い、ひどくならないうちに医療機関を受診して、せきがこれ以上長期化するのを防ぎましょう。
参考文献
日本呼吸器学会「咳嗽と喀痰の診療ガイドライン第2版」2025









































